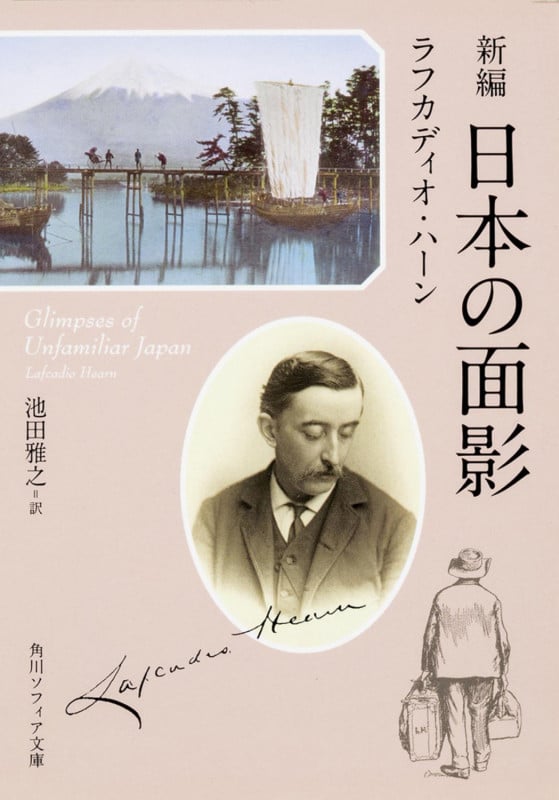鹿島アントラーズ2-0柏レイソル
J1百年構想リーグEAST・第3節/2026年2月21日(土)16:00/メルカリスタジアム/DAZN
去年はリカルド・ロドリゲスのもとで大躍進を遂げ、最後まで激しい優勝争いを繰り広げたレイソルだったけれど、今大会は初戦で川崎に5-3という大乱打戦のすえに負け、前節もヴェルディに逆転負けをくらって、ここまで2連敗。序盤から苦しい戦いを強いられている。
前節は後半ロスタイムに原田がレッドカードで退場してしまい、この試合は出場停止だったので、3バックは古賀を中心に、右が24歳の馬場、左が元鹿島の杉岡という組み合せで、三丸を左サイドウィングに起用していた。
なぜにいつもはCBの三丸とSBの杉岡のポジションを入れ替えたのかわからない。調べたら三丸よりも杉岡のほうが背が高いので、高さを買ったということなのかもしれない。初戦から守備が綻びているので、なんとかしたいという苦肉の策なのかも。
対する鹿島は前節は出場停止だった三竿が戻ってきて、樋口とコンビを組んだ。
前節は決勝点の起点となった柴崎と、精力的に最後まで足を止めなかった樋口、どちらも好印象だったので、今節のボランチの組み合わせはどうなるか注目していたのだけれど、鬼木の選択は三竿と樋口だった。今季のボランチの軸は三竿ってことらしい。
スタメンではあと両SBが濃野と溝口だったのが前節との違い。
まさか決勝点をアシストした小川をはずして溝口を使ってくるとは思わなかった。鬼木の起用法って地味な意外性がある。その試合で足を痛めて途中交替した小池はベンチ外だった。
この試合のひとつめのポイントとなったのは、前半なかばに早川がPKを取られたシーン。右SWの山之内(22歳のこの選手はかなり目立っていた)がゴール前でボールを受けようとしたところへスライディングしてクリアにいってファールを取られた。まぁ、ボールにはいっていたし、あのファールは致し方なし。運がなかった。
でも細谷がキッカーを務めたこのPKを早川は見事に止めてみせた。しかもゴールど真ん中へのキックを微動だにせずにがっしりと胸で受け止めて。あんな動きの少ないPK、初めて見たよ。なにごとかと思った。
ちなみにああいう真正面へのキックって、それを得意にした選手の名前にちなんでパネンカと呼ぶらしいっすね。初めて知った(でもきっと覚えられない)。
このPK阻止で窮地を脱した鹿島は、その10分後にセットプレーから先制に成功する。
ゴールに向かって左手から蹴った樋口のFKがファーに流れたのでミスキックかと思ったら、そこへ駆け込んだ優磨が右足でダイレクトに折り返し、ゴール真正面でフリーになっていたレオ・セアラへ絶妙なアシストをかます。レオもダイレクトで右足を振り抜いて、豪快にゴールネットを揺らしてみせた。なんちゅう気持ちのいいゴール!
後半の追加点も樋口のセットプレーから。右コーナーから蹴り込んだ高速クロスに植田が頭であわせた。これもお見事のひとことだった。クロスのスピードにも、それにあわせた植田の技術にもびっくり。
守ってはかつての川崎のような細やかなパス回しで相手を翻弄するシーンも見られたし、この日もシュートこそ8本と少なかったけれど、内容的には鬼木に監督になって以来、最高の出来といえる試合だったんじゃなかろうか。3連敗で最下位に沈んだままの柏はお気の毒さま――としかいえない。
途中出場は小川、林、知念、チャヴリッチ、徳田の5人。全員スコアが2-0になってからの交替だった。この日の林はなるほど期待されるだけのことはあるのかもという小気味よいプレーを見せてくれていた。
柏でも最後のほうに垣田と仲間が出てきた。ふたりとも今期はこれが初出場。杉岡はフル出場で、ベンチには犬飼もいた。鹿島を離れた選手たちの活躍を見るのもサッカーの楽しみのひとつだ。
(Feb. 23, 2026)