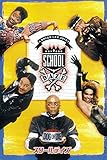リコリス・ピザ
ポール・トーマス・アンダーソン監督/アラナ・ハイム、クーパー・ホフマン/2021年/アメリカ/Apple TV
ハイム三姉妹の末娘、アラナ・ハイムを主演に起用したというので気になっていたポール・トーマス・アンダーソ監督の2021年のアカデミー賞ノミネート作品。最新作の『ワン・バトル・アフター・アナザー』が話題になっているこのタイミングで、遅ればせながらようやく観た。――って、もう五年も前の映画なのか! そりゃびっくり。
もうひとつ驚いたのは、出ているのがアラナだけではなかったこと。姉のエスティ、ダニエルもそのまま三姉妹の役どころで出ている。しかも役名は三人とも本名と同じ(さすがに苗字はハイムではない)。さらには彼女たちの両親を演じているのも実の親御さんたちだそうで、つまりハイム一家が総出で出演しているのだった。なんだそりゃってキャスティング。
アラナの相手役を務める主役のクーパー・ホフマンは、いまは亡きフィリップ・シーモア・ホフマンの息子さんだそうで、そういわれると、なるほど父親に似ている。2003年生まれだそうだから、このときまだ十代で、演じているのは十五歳の役だから、まぁ年相応なわけだ。ぽっちゃり体系で、いまいちそうは見えないけれども。彼もこれがデビュー作とのこと。
対するアラナ(このころはすでに三十歳近い)は二十五歳という設定。
これはそんな十歳年の離れた年の差カップルの話で、しかも冒頭から男の子が彼女に一目惚れをするという展開――なのですが。
失礼ながらアラナさん、美人というタイプではないので、その展開に戸惑ってしまった。いったいなぜ彼が彼女を見初めるのか、よくわからない。
物語的には、典型的な美男・美女を配したほうが納まりがいいのに、あえてそうしていないところがこの映画のポイントなのだと思う。いまの時代ならではの反ルッキズムのたまものなのかもしれない。
映像はわざと七十年代っぽいテイストで撮ってあるし、使われている音楽もその時代のものだし、全体的に七十年代の青春恋愛映画って作りなのに、主演のふたりの存在がそういう典型からはずれているところに、珍妙な味わいが生まれている――気がしないでもない。『リコリス・ピザ』という意味不明なタイトルも、その辺のずれを象徴しているのかもしれない。
そもそも、ホフマンはいまいち高校生には見えないだけではなく、彼の演じるゲイリーは、すでに子役として稼いでいて、ウォーターベッドを売ったり、ピンボール店をオープンしたりと、やたらと商売っ気がある、高校生らしからぬ役どころだ。
対するアラナは年よりも若く見えて、逆に彼女のほうが高校生といっても通りそうな頼りない感じなので、いったいどっちが年上なのか、よくわからない。少なくても十才も歳の差があるようには見えない。そんな物語とキャスティングのミスマッチが変てこりんな味わいを生んでいる。
脇ではショーン・ペンがウィリアム・ホールデンをモデルにした俳優役を演じていて、そんな彼と親しい映画監督役で、なんとトム・ウェイツも出演している(ふたりとも妙に楽しそう)。さらにはバーブラ・ストライサンドの恋人だったという実在の映画プロデューサー、ジョン・ピーターズ役がブラッドリー・クーパー(いわれないとわからない)。
主演に映画初出演のふたりを配しながら、脇役にそんな豪華なキャスティングをしてみせたのもこの映画の見どころのひとつかもしれない。
(Jan. 25, 2026)
ストレンジャー・シングス シーズン5
ザ・ダファー・ブラザーズ制作/ウィノナ・ライダー、デイヴィッド・ハーパー、ミリー・ボビー・ブラウン/2025年/アメリカ/Netflix(全8話)
海外の配信作品では年末一の話題作って感じだった『ストレンジャー・シングス』の最終シーズン。
残念ながら今シーズンはシリーズでもっとも出来が悪いと思った。つまらなかったとまではいわないけれど、ひっかかるところが多すぎて、どうにも楽しみ切れなかった。
このドラマはいたいけな子供たちやふつうの人々が、未知のモンスターに襲われて右往左往しながらも、なんとか事態を切り抜けてゆくスリリングさが魅力だったのに、今回は主要キャラがやたらと暴力的なのがとにかく駄目。
彼らはホッパーとエルを中心にしたアンダーグラウンドのゲリラ勢力みたいになっていて、ホッパーはアーミーに対して平気で銃を乱射したり、手榴弾を投げつけたりする。ナンシーまでライフルを撃ちまくる展開においては、なんだそりゃだ。人を殺すことに対してなんの躊躇も逡巡もないところに違和感ありまくり。
終盤でダスティンやスティーヴがランボーみたいな服装をしているので、『ランボー』に代表される八十年代のアクション映画へのオマージュのつもりなのかもしれないけれども、だとしたらちょっとピントがずれすぎではと思う。
モンスターと戦うのならばともかく、同じ人間どうしで殺しあっちゃ駄目でしょう? 己の信じる正義のためならば他人の命を奪うのもやむなしという発想には、最近のベネズエラ侵攻に通じるアメリカの自分勝手さを感じる。普段ならそれほど気にならなかったのかもしれないけれど、観たのがちょうどその軍事侵攻の直後だったので、なおさら駄目な気がした。
たかがエンタメ、されどエンタメ。政治と娯楽がともに他人の命を奪うことになんの罪悪感も覚えていないようなアメリカ人の倫理観には疑問しかない。
このドラマに関しては、新型コロナウィルスや業界のストライキによる中断期間が挟まったために、主演の子供たちが成長してしまったのが最大の痛手だったように思う。
子供のままだったら、もうちょっと節度のある展開が期待できたかもしれないのに、なまじ大人になってしまっただけに(まぁ、物語の中ではいまだ高校生という設定だけれども)イージーなアクション任せなシナリオになってしまった気がする。
あと、ラスボスを前作で登場したヴェクナにしてしまったのも個人的には失敗だと思った。もともと人間だったキャラを倒せば世界が救えるという展開にはどうにも説得力がない。最後にそのキャラの首を落として終わりという残虐さについても、なんでそうなるのと思わずにいられなかった。
最終話では二時間という映画並みの尺をとってクライマックスを描いたあとに、後日談として平和になった世界をたっぷりと見せてくれているけれども、それまでの展開があんまりだったものだから、どうにもハッピーな気分になれない。
とにかく、アメリカという国が潜在的に持つ暴力性が、エンタメとして悪い形で噴出してしまったような完結編だったと思う。残念。
(Jan. 12, 2026)
F1 ザ・ムービー
ジョセフ・コシンスキー監督/ブラッド・ピット、ダムソン・イドリス、ケリー・コルドン/2025年/アメリカ/Apple TV+
車も持っていないし、モータースポーツにも興味はないのに、不思議とこの手の映画は観たくなる。
F1団体の全面サポートを受けたとかなんとかいう噂の、ブラッド・ピット主演のF1レース映画。
――だと思って観始めたら、いきなり最初のレースはF1ではなく、デイトナ24時間耐久だった。
ブラピ、F1ドライバーじゃないじゃん!
――という意表をつく始まり方をしたこの映画。
ブラッド・ピット演じる主人公のソニー・ヘイズは、30年前の若き日に事故でキャリアを棒に振ったレーサー。F1にこそ乗っていないけれど、ドライビングにおけるセンスは天才的で、様々なレースに参加しては結果を残している――らしい。
そんな彼にかつてのチームメイトだったハビエル・バルデム(いまだに名前が覚えられない)から、自分がオーナーを務める新参F1チームで走ってくれないかとオファーがある。今季1勝もしていない彼のチームはこのままだと身売りせざるを得ないという状況にあり、ブラピの才能を知ったるかつての旧友が、その天才に一か八かの賭けをすることにしたわけだ。
F1に復帰するには歳をとりすぎているブラピ(実年齢62歳!)に、チームも世間も疑いの目を隠さない。とくにチームの黒人エースドライバー、ジョシュア(ダムソン・イドリス)は反発することしきり。それでもソニーは持ち前の才覚と、反則ぎりぎりの手管を厭わないずるがしこさでもって、チームに多大な貢献を果たすようになり、周囲の信頼を得るのみならず、そのシーズンの主役のひとりになってゆく。
年配者が若者とためをはって戦うという展開には、晩年の『ロッキー』を思い出させるところがあるし、F1のサーキットで世界中をまわりながら、でこぼこだったチームが徐々に団結してゆく展開には少年ジャンプ的な楽しさがあった。
決して傑作とは思わないけれども、そんな風にマンガ的だからこそ、いずれまた観たくなるんだろうなって思った。
(Dec. 27, 2025)
シーズ・ガッタ・ハヴ・イット
スパイク・リー監督/トレイシー・カミラ・ジョンズ、トミー・ヒックス、ジョン・カナダ・テレル/1986年/アメリカ/Netflix
一時間半くらいと短めだったこともあり、せっかくだからつづけてこれも観てしまうことにした。スパイク・リーの監督デビュー作がこちら。
これも昔観たときにはぴんとこなかったんだけれど、『スクール・デイズ』とは違い、今回はよかった。スパイク・リーの父親、ビル・リーの手掛けるジャズのサウンドトラックと、白黒のスタイリッシュな映像の組み合わせがぴったりで、観ていてとても心地よかった。この気持ちよさにはジャン=リュック・ゴダールの作品に通じるものがあると思った。
内容は、性的に奔放なひとりの女性(トレイシー・カミラ・ジョンズ)と、彼女とつきあう三人の男性――トミー・ヒックス、スパイク・リー、ジョン・カナダ・テレル――とのいびつな関係を、彼らへのインタビューで描きだすという疑似ドキュメンタリー風のコメディで、物語的にはそれほど惹かれないんだけれど、映画としての質は高いと思う。これが日本ではこれまでVHSでしかパッケージ化されていないのって、いささかひどいのでは?――と思ってしまった。ネトフリが配信してくれててよかった。
この映画には『スクール・デイズ』と同じくスパイク・リーの妹ジョイ・リーのみならず、父親のビル・リーも出演していた(主人公の父親役)。そんな風に家内手工業的なキャスティングでもって、こういうスタイリッシュな映画を撮ってみせた若き日のスパイク・リーの才気が溢れる逸品。
エンドクレジットで、彼ら出演者がそれぞれ自分たちの名前が書かれたカチンコを持って自己紹介するのも素敵でした。
(Nov. 24, 2025)
スクール・デイズ
スパイク・リー監督/ラリー・フィッシュバーン、ジャンカルロ・エスポジート/1988年/アメリカ/Apple TV
スパイク・リーのファンを自称しながら、僕はとんでもない勘違いをしていた。
いまのいままで、この『スクール・デイズ』が彼のデビュー作だと思い込んでました。
『シーズ・ガット・ハヴ・イット』のほうが先かよ……。
まぁ、この初期の二作品については、正直あまり思い入れがなくて、これまで一度ずつしか観ていないし、たぶんどちらも同時期に観て、それきりだったので、記憶が改ざんされてしまったらしい。内容的にもこれのほうが『シーズ・ガット・ハヴ・イット』よりも若気の至りな感が強いし。
黒人大学での寮生どうしのバカ騒ぎとセックスを描いたこのコメディ。学校とか集団行動が苦手な僕は、残念ながらまったく楽しめなかった。もしもこれが最初に観たスパイク・リー作品だったとしたら、もしかしたら僕は彼のファンを公言していないかもしれない。最近だと『シャライク』が同系列の作品で(それゆえ僕は駄目だった)、あれはこの続編だったんじゃないかって気がする。
この映画で(やや誇張して?)描かれるようなアメリカの大学のカルチャーって、なんか違和感がはんぱない。こんな世界には絶対に馴染めない。なんでジャンパー着ているシーズンに、ダンスパーティーで水着になるのかもわからない。風俗的にも苦手な八十年代が舞台だし、個人的には好きになれる要素がほとんどなかった。
まぁ、あえていうのならば、ミュージカルと呼んでもいいくらい、音楽シーンがたくさんあるので、八十年代末のブラックミュージックのショーケース的な見方をすると、いくらか楽しめそうな気もする。あと、ジャンカルロ・エスポジート(今回初めて名前を認識しました)をはじめ、ビル・ナンやサミュエル・L・ジャクソンら、スパイク・リー作品の常連さんたちがたくさん出ているので、そういう人たちの若き日の姿が観られるのは貴重かもしれない。
主演のラリー・フィッシュバーンって誰かと思ったら、ローレンス・フィッシュバーンのことだった。若いころはスリムでカッコよかったんだ。
そういや、スパイク・リーが演じるキャラが字幕では「ボーヤ」と呼ばれているのに違和感があって、英語だとなんといっているのか調べてみたら「Half-Pint」だった。「半パイント」しかない小さなやつというスラングらしいので、それだったら「ボーヤ」より「チビ」のほうが自然じゃん? と思ったんだけれど、もしかしていまや「チビ」は差別用語扱いで使えないのか。「でぶ」とかも駄目なのかな。いろいろ面倒臭い時代だなぁと思う。
(Nov. 22, 2025)