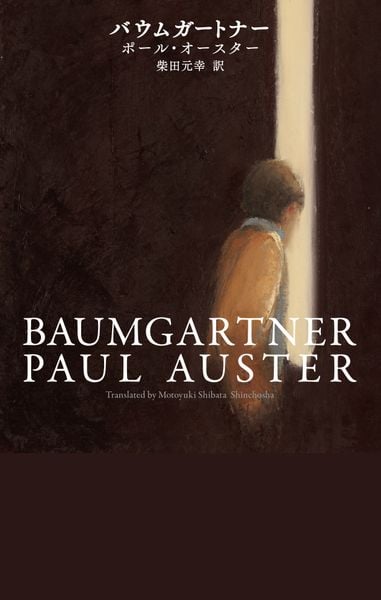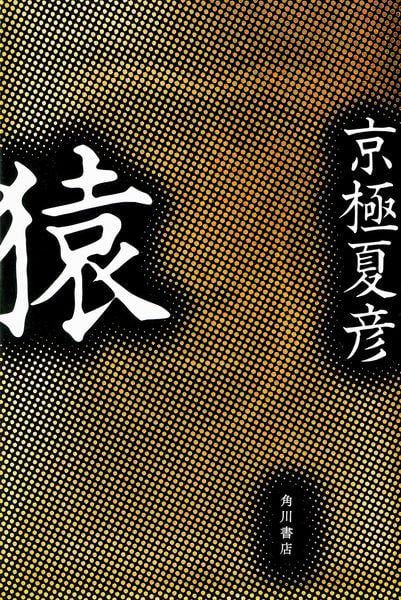ブラウン神父の知恵
G・K・チェスタトン/中村保男・訳/創元推理文庫/Kindle
前作を読んでからだいぶ間があいてしまった。およそ三年ぶりに読むブラウン神父シリーズの第二弾。
『ブラウン神父の童心』では相棒フラウボウとの出逢いから彼が改心するまでの展開が、連作短編的な形で含まれていたけれど、今回はそういう仕掛けはなくて、ふつうに短編集って感じになっている。
特徴があるとすれば、犯人探しやミステリとしての体裁よりも謎解きのサプライズを主眼にした作品が多いところ――だろうか。
たとえば最初に収録されている『グラス氏の失踪』では、ブラウン神父が高名な犯罪学者だという人を訪ねていって事件の解決を依頼するのだけれど、結局その人の推理は的はずれで、ブラウン神父がその間違いを正して終わる。なぜ自分で説明できる事件のためにブラウン神父がその人を呼びにいったのか、まるでわからない。
そのほかの短編もほぼすべてが「こういう事件がありまして、こう思われていますが、じつは真相はこうです」とブラウン神父が解き明かしてみせる形。でもって、真相はピンポイントで明かされるものの、事件の顛末自体はなんとなくあいまいなままで終わってしまう話が多い――ような気がした。
まぁ、今回も途中で寝落ちしてばかりで、ちゃんとディテールを読みとれてない感が強かったので、きちんと読めばわかることを、僕がわかっていないだけってことなのかもしれない。前のときもそんな感じだったし、なんとなくチェスタトンとは相性が悪い気がする。
あと、とにかくこのシリーズは翻訳が古い。ブラウン神父がフラウボウに「おまえさん」と呼びかけたり、登場人物が自分のことを「吾輩」と呼んでいたりする。時代劇でもあるまいし。いまどき「吾輩は」といってもおかしくないのは猫くらいだろう。
本当にこのシリーズを後世に残すべき傑作だと思っているならば、そろそろ新訳に入れ替えることを考えてしかるべき時期なのでは。
(Feb. 18, 2026)