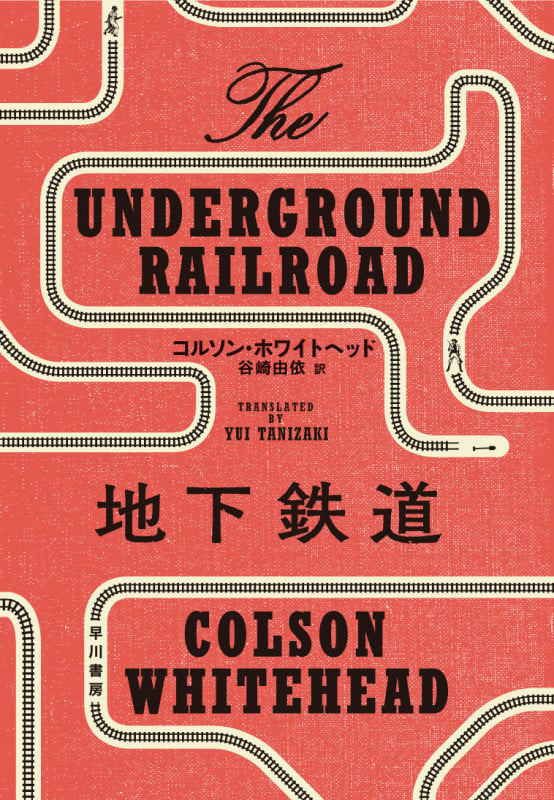ものすごくうるさくて、ありえないほど近い
ジョナサン・サフラン・フォア/近藤隆文・訳/NHK出版
これも先月読んだ『オスカー・ワオの短く凄まじい人生』と同じ2011年に刊行されたアメリカ文学の翻訳作品。でもって主人公の名前もたまたま同じオスカー。
ただ、こちらのオスカーくんは九歳の男の子。大変早熟でませた口をきく(ある種の天才少年?)。彼は同時多発テロ事件で父親を亡くしていて、そのショックからいまだ立ち直れずにいる。
そんな彼がある日、父親の持ち物のなかから謎の鍵を見つける。鍵が入っていた封筒には「ブラック」という文字。それが鍵の秘密を知る関係者のラストネームだとあたりをつけた彼は、鍵がなにを開けるためのものかを突き止めなきゃならないと心に決めて、ニューヨーク中のブラックさんたちを訪ねて歩く決意をするのだった。――その数二百十六軒。
まぁ、そんなことあるかいって話ではあるんだけれど、少年のエキセントリックなキャラクター設定からしてある種のファンタジーっぽさがあるし、彼が出会う大人たちは軒並み善人ばかりだし、これは心に傷を負った少年の癒しを描いたある種の寓話として楽しむべき作品なのではという気がした。とてもよいです。
この小説がすごいのは、そんな少年の寓話的な冒険譚と並行して、第二次大戦時にドレスデン大空襲を経験した彼の祖父母のドラマをもうひとつの軸として描いている点。イノセントでコミカルなオスカー少年の物語とは対照的に、そちらは痛々しくてセクシャルだ。オスカーの話だけだと甘くなりすぎてしまいそうなところに、祖父母の過酷な人生を並列してみせた、そのバランス感覚が見事。
さらにはヴィジュアル・ライティングというやつで、文章の見せ方にもたくさんのアイディアが施されている。行間が徐々に詰まっていって、最後には活字が重なり合って真っ黒になってしまうページがあったり、校正の赤ペンが入っているページがあったり。一ページに一行だけしか文章がないページがつづいたり。物語のなかに出てくる写真もたくさんインサートされていて、最後はパラパラ漫画のようになっていたりする。
ということで、小説としてだけでも十分すぎるくらいの出来なのに、さらにはそこに小説だからこそ可能なヴィジュアル面での創意工夫まで加わっているという。小説という表現形式の可能性をどこまで広げられるか、考え抜いた末に生まれてきたような素晴らしい作品。この内容ならば映画化されたのも当然だ。そちらもぜひ観たくなった。
そうそう、作者のジョナサン・サフラン・フォアの奥さんが『ヒストリー・オブ・ラヴ』のニコール・クラウスだってのもびっくり。なにその夫婦。すごすぎる。
(Mar. 07, 2022)