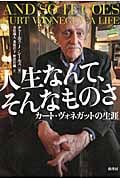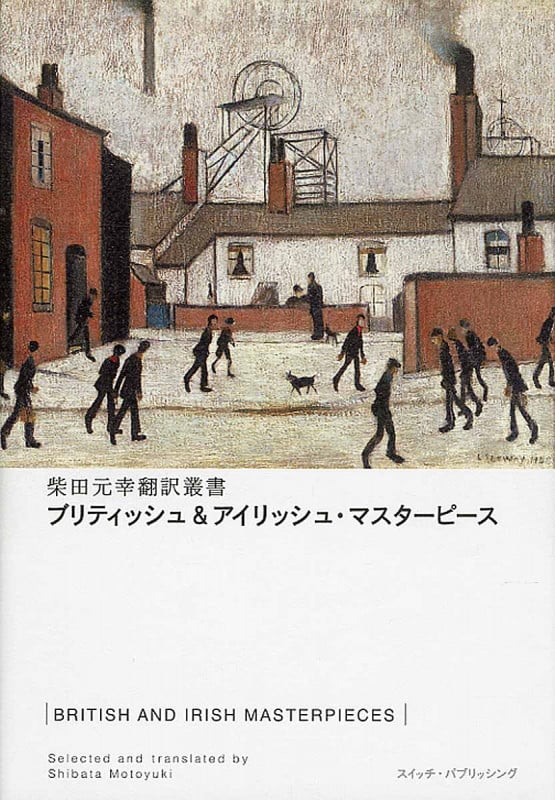数学者たちの楽園 「ザ・シンプソンズ」を作った天才たち
サイモン・シン/青木薫・訳/新潮社
『ザ・シンプソンズ』に絡めて数学を語ったエッセイ集ということで、刊行された頃からずっと気になっていた本。
でも買いもしないうちに月日が過ぎて、はや十年。最近になって作者が『フェルマーの最終定理』のサイモン・シンであることに気づき、「ならばなおさら読まなきゃじゃん!」と思って、先日重い腰をあげて買ってきた。
さすがにそれだけ時間がたっているので、すでに新潮文庫にも入っているのだけれど、そちらは背表紙がシルバーだったので、「やっぱシンプソンズ絡みならば全部黄色でないと」と思って、あえて単行本を買いました。老後のたくわえを心配しつつ。プチ贅沢。
この本で意外だったのは、これが本当にシンプソンズについての本だったこと。
スティーヴン・ジェイ・グールドの『パンダの親指』が、タイトルに「パンダ」とあるにもかかわらず、パンダについてのエッセイが表題作一本だけしか収録されていないのと同じように、これもシンプソンズの話題は一部だけかとかと思っていたら、そうではなかった。ほんと全部が『ザ・シンプソンズ』にまつわるエッセイ。
いや、正確にいうと、最後の四本は『フォーチュラマ』についてだけれど、それも制作者がシンプソンズと同じ姉妹編と呼べる作品だからであって、主役がサブタイトルにある『「ザ・シンプソンズ」を作った天才たち』であることには偽りがない。
なんでも『ザ・シンプソンズ』の脚本家チームには、学生時代に数学やそのほかの理系学部で博士号・修士号を取った数学オタクな人たちがわんさといて、その専門知識をわかる人にわかればいいというレベルのジョークとして、アニメの小ネタに忍ばせているのだそうだ。それもこんな本が一冊かけてしまうくらいたっぷりと。
ということで、この本は『ザ・シンプソンズ』に出てくる様々な数学ネタを――ふつうの人には気づきさえしないような数字の数々を――ピックアップして紹介してゆく。
それこそフェルマーの最終定理や、素数、完全数、無理数、円周率といった純数学的な話から、セイバーメトリクスやナード・ギークなオタクな話題まで、多種多様な数学ネタが取り上げられている。文系の僕には理解しきれない部分もあったけれど、『フェルマーの最終定理』と同じで、決して難し過ぎはしない絶妙のさじ加減なので、十分に楽しめる内容だった。さすがサイモン・シン。
惜しむらくは『The Simpsons And Thier Mathematical Secrets』(ザ・シンプソンズと数学の秘密)という原題が『数学者たちの楽園』という邦題に変わってしまって、肝心の「ザ・シンプソンズ」がサブタイトルに追いやられている点。
まぁ確かに原題のままだと、シンプソンズの本だと思って読んだ人が面食らってしまいそうだし、数学好きな人が手に取る可能性が下がりそうな気もするので、出版事情をかんがみれば正しい判断なのかもしれない。
それでも主役であるはずの「シンプソンズ」がサブタイトルに甘んじてしまっているのは、やっぱちょっと残念だ(それゆえに僕が内容を勘違いしたわけだし)。原題は『パリ―・ポッターと賢者の石』等を意識したものだろうし、作者の遊び心にこたえる意味でも、できればそちらに寄せて欲しかった。
翻訳家の青木薫という人は『フェルマーの最終定理』ほか、理数系のエッセイ集を中心に手掛けている人で、『ホーマーの三乗』という章の冒頭では、パティ―とセルマを「ホーマーの義理の妹」と書いているくらいだから、あまり熱心なシンプソンズのファンではないんだろう。シンプソンズと数学を秤にかければ、数学に傾くのは必至――そういう人がタイトルをつけたら、こうなるのは当然の帰結のような気もする。
あ、でも英語ができる人は、吹替ではなく英語のまま字幕なしで観るせいで、「シスター」が姉か妹か、判別できなかったりする可能性もある?
いずれにせよ、パティ―とセルマはホーマーの義理の「姉」です(ウィキペディア英語版にも「older sister of Marge」とある)。もしかしたら文庫版では直っていたりするのかもしれない。
(Jul. 02, 2025)